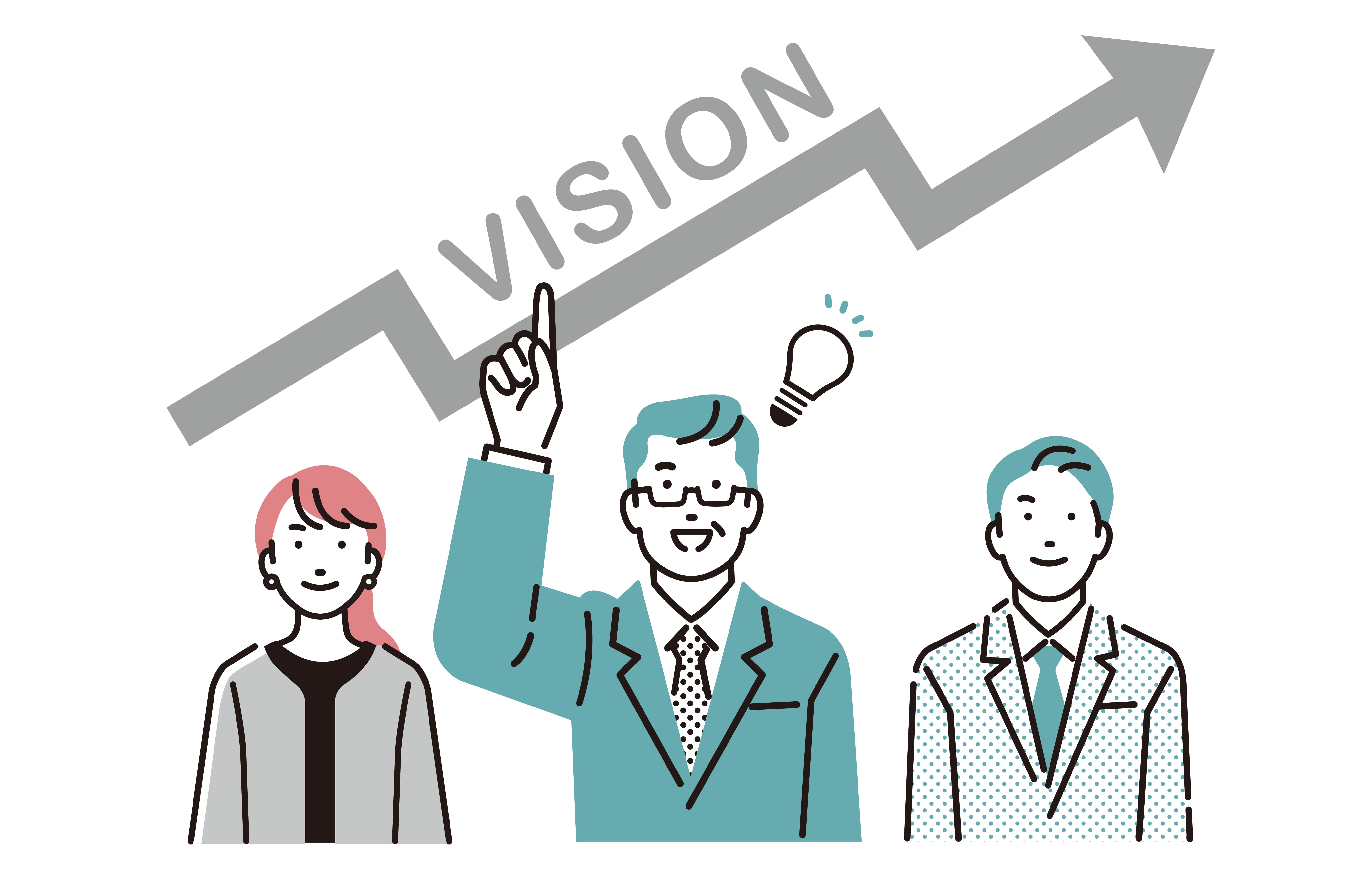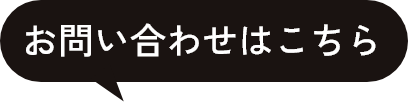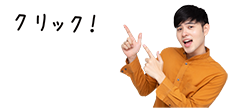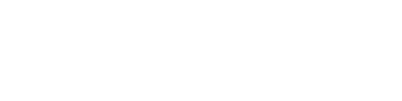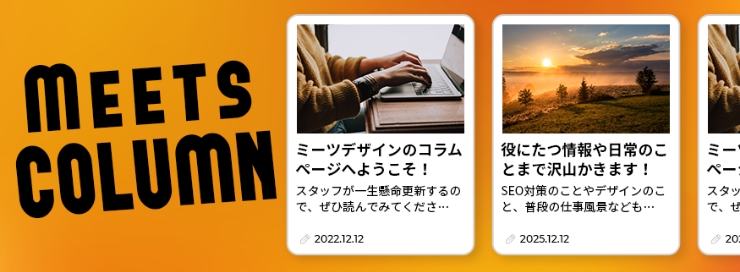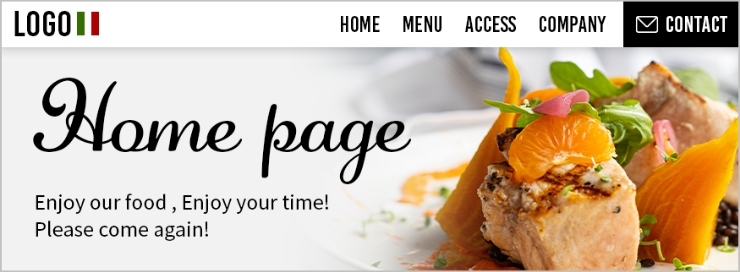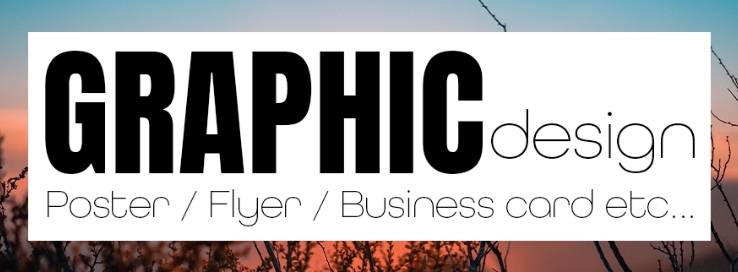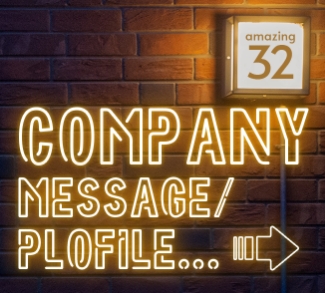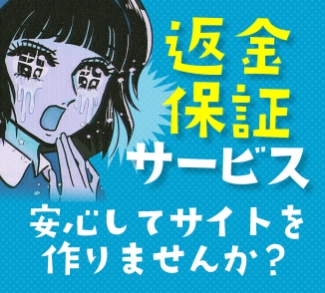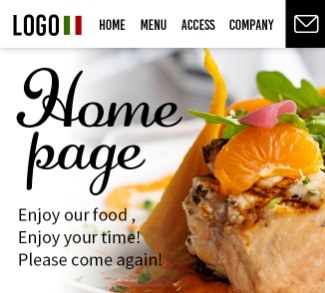なぜホームページ制作会社で料金が違うのか?発注前に知っておくべき5つの理由


ホームページを制作しようと複数の会社に見積もりを依頼すると、料金に大きな差があることに驚く方は多いでしょう。
「同じホームページなのに、なぜ数十万円単位で違うのか?」
これは発注者の誰もが抱く素朴な疑問です。
本記事では、制作会社ごとに料金が異なる 5つの主要な理由 を解説します。発注前に理解しておけば、適切な判断基準を持ち、無駄のない選択ができるはずです。
理由1:制作の目的と戦略設計の有無
料金差の最も大きな要因は、戦略設計を行うかどうか です。
-
・低価格のプランでは「見た目のデザイン」や「必要最低限のページ制作」が中心で、戦略的要素は省かれがちです。
・一方、しっかりとした会社では「ターゲット分析」「競合調査」「情報設計」など、成果につながる仕組みを最初に構築します。
つまり、戦略の有無が料金を分ける分岐点。
「会社案内として最低限あればよい」のか、「集客や採用で成果を上げたい」のか。目的に応じた選択が大切です。
実際にどのように戦略設計が活かされるのかは、戦略設計の事例コラム で詳しく紹介しています。
理由2:デザインのクオリティとオリジナリティ
料金を左右する次の要素は、デザインの質と独自性 です。
-
・テンプレート利用:低コストで短納期。ただしオリジナリティやブランド性は弱い。
・オリジナルデザイン:企業の強みや個性を反映し、信頼性を高められる。その分コストは高め。
さらに、UI/UX(ユーザー体験)を意識して「行動を促す導線」を設計しているかどうかも大きな差となります。
単なる“綺麗な見た目”ではなく、成果を出すためのデザインが料金に反映されます。
理由3:システムや機能の有無
必要な機能の範囲によっても料金は変わります。
-
・問い合わせフォームのみ → 数万円レベルで実装可能
・会員登録・予約システム・EC機能 → 数十万〜数百万円規模に拡大
例えば、医療機関の「予約システム」や不動産サイトの「物件検索機能」は大きなコスト差を生みます。
「何を実現したいか」を明確にすることで、見積もりが比較しやすくなります。
理由4:制作体制と担当者の関わり方
制作会社によって、どのような体制でプロジェクトを進めるかも料金に影響します。
-
・大規模な会社では、ディレクター、デザイナー、エンジニア、ライターなど専門職が分業体制で関わり、安定した品質を確保します。
・規模にかかわらず重要なのは、経験豊富な担当者がどの段階で責任を持って関わるか。直接的なコミュニケーションや一貫したサポートがあるかどうかは、大きな価値になります。
料金を比較する際には、「体制の人数」ではなく、プロジェクトへの関わり方と担当者の質を確認しましょう。
理由5:公開後のサポート・運用体制
「作って終わり」か「育て続ける」かで、長期的な費用は大きく変わります。特に 営業の方向性がアウトバウンド中心なのか、インバウンド集客を重視するのか によっても、最適な選択は異なります。
-
・アウトバウンド(訪問営業や紹介がメイン)の場合は、シンプルなサイトで十分なケースもあります。
・インバウンド(検索や問い合わせ獲得が目的)の場合は、公開後も改善を続けられる運用サポートが効果的です。
つまり、自社の営業戦略に合わせて「どこまで運用を必要とするか」を見極めることが重要です。
まとめ
ホームページ制作の料金は「会社ごとにバラバラ」ですが、その理由を紐解くとシンプルです。
違いを生むのは、
-
・戦略設計の有無
・デザインの質
・機能の範囲
・担当者の関わり方
・公開後のサポート
大切なのは、自社の目的と重なる部分に適切に投資すること。
料金の高低だけで判断せず、目的に合ったパートナーを選ぶことが、成果につながる第一歩です。
もし「自社に合った制作会社をどう選べばいいか分からない」「具体的に料金感を知りたい」とお考えでしたら、ぜひお気軽にご相談ください。